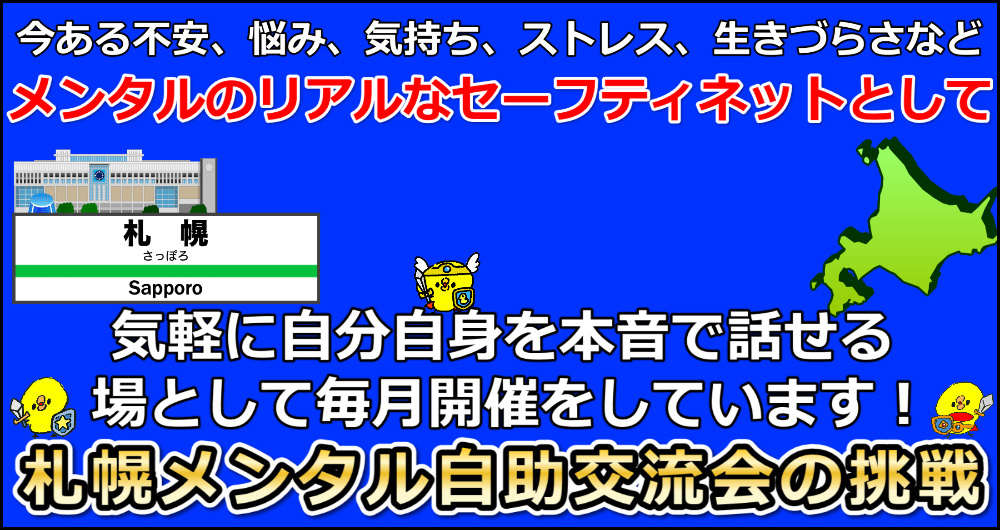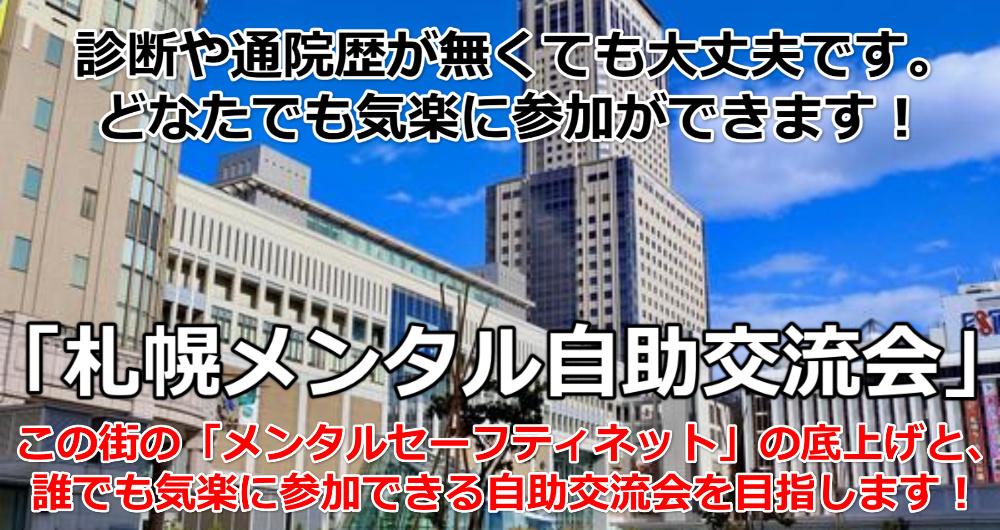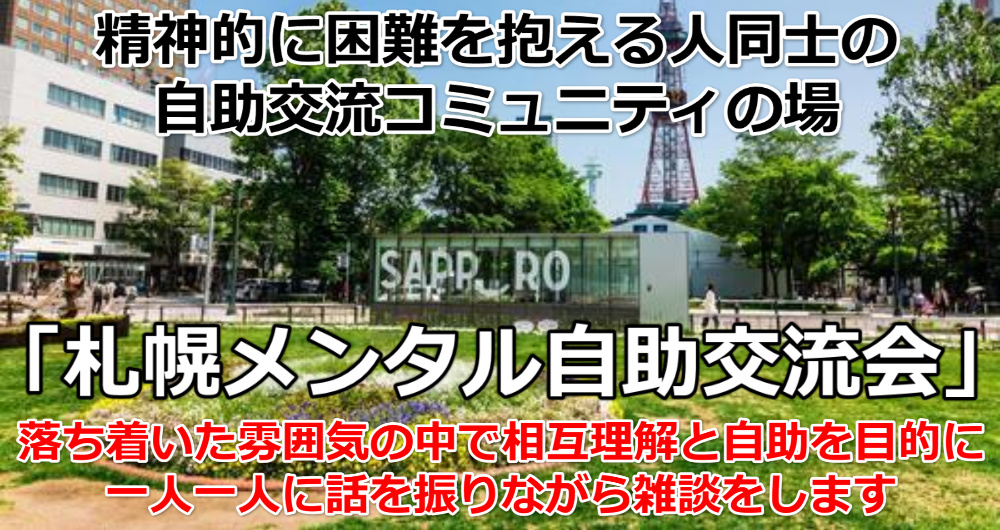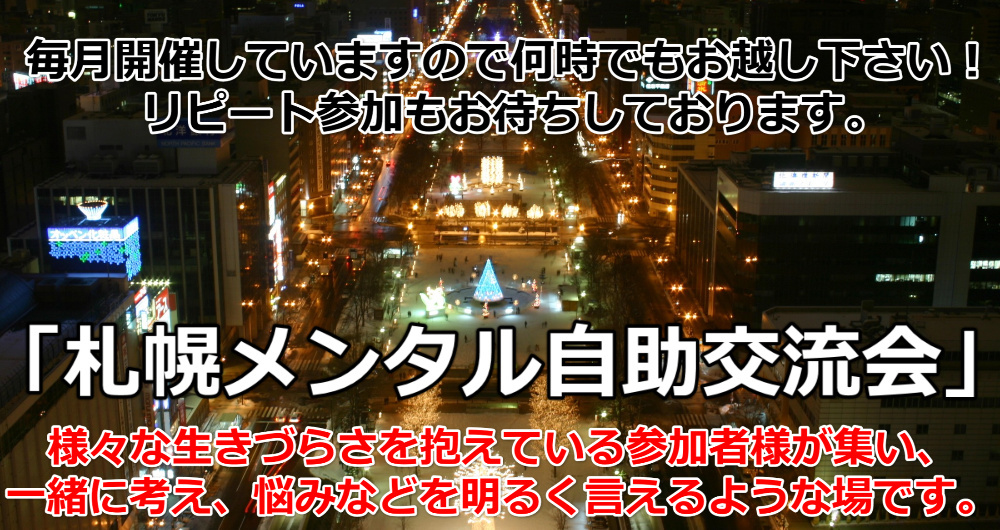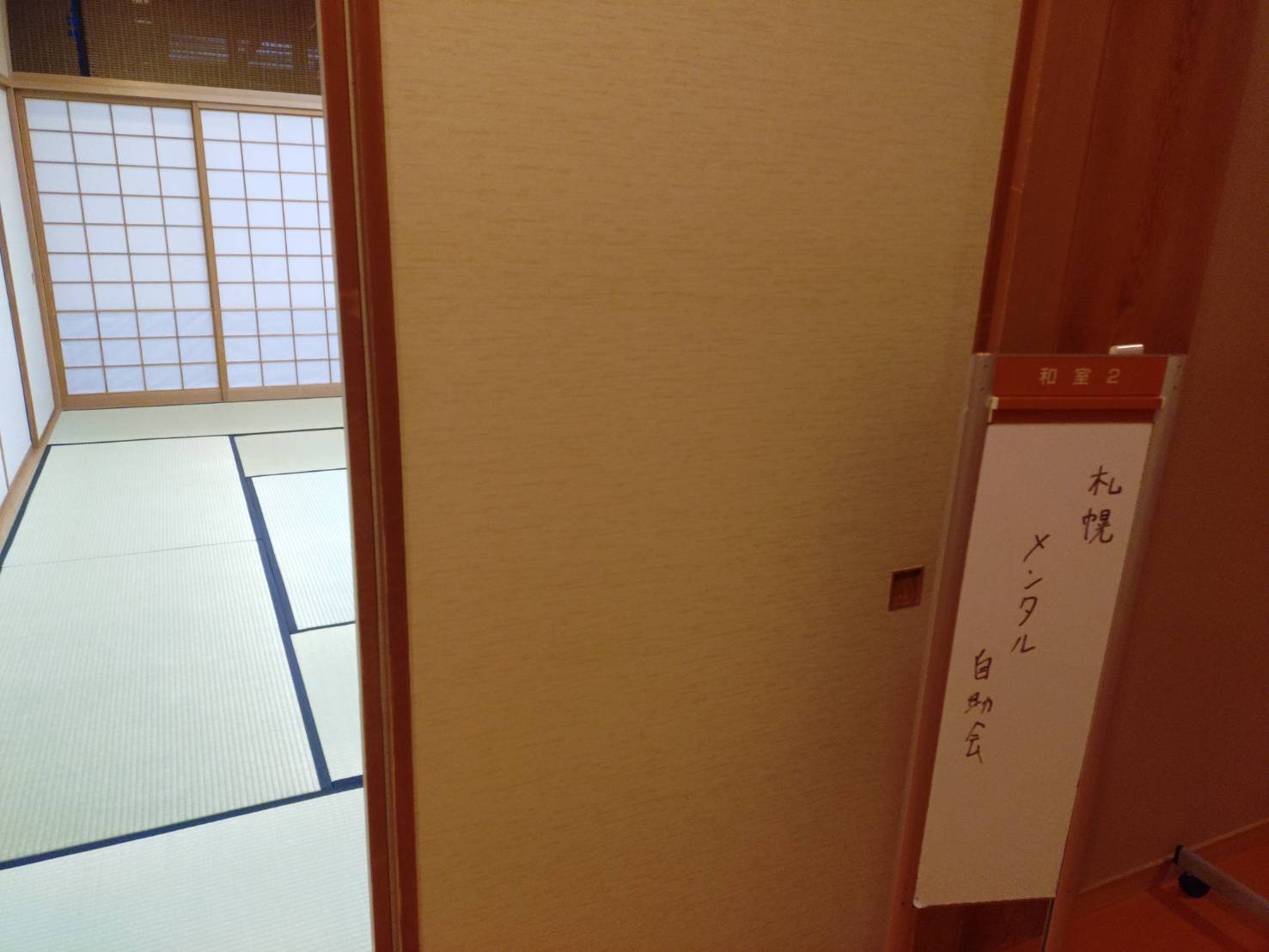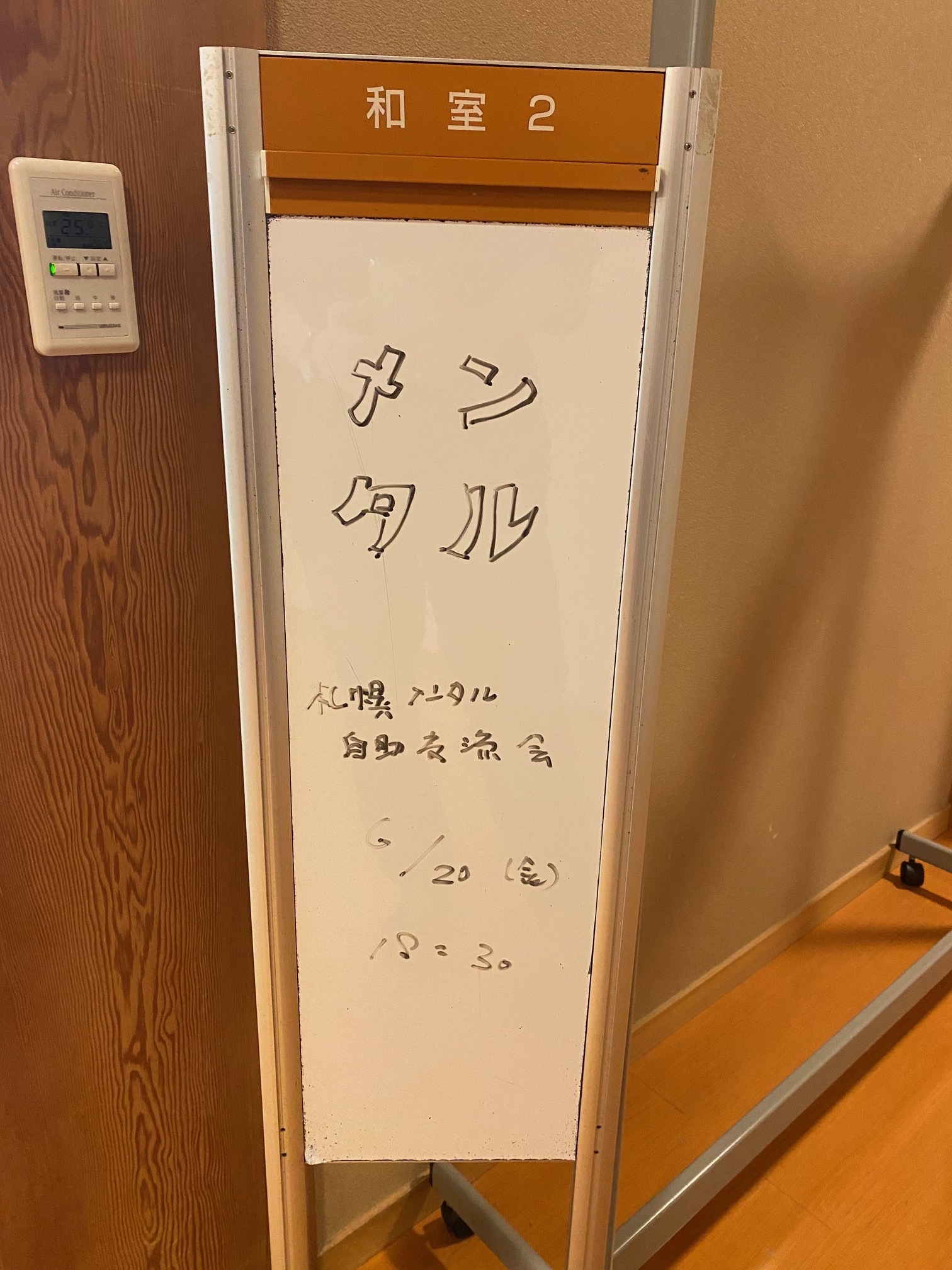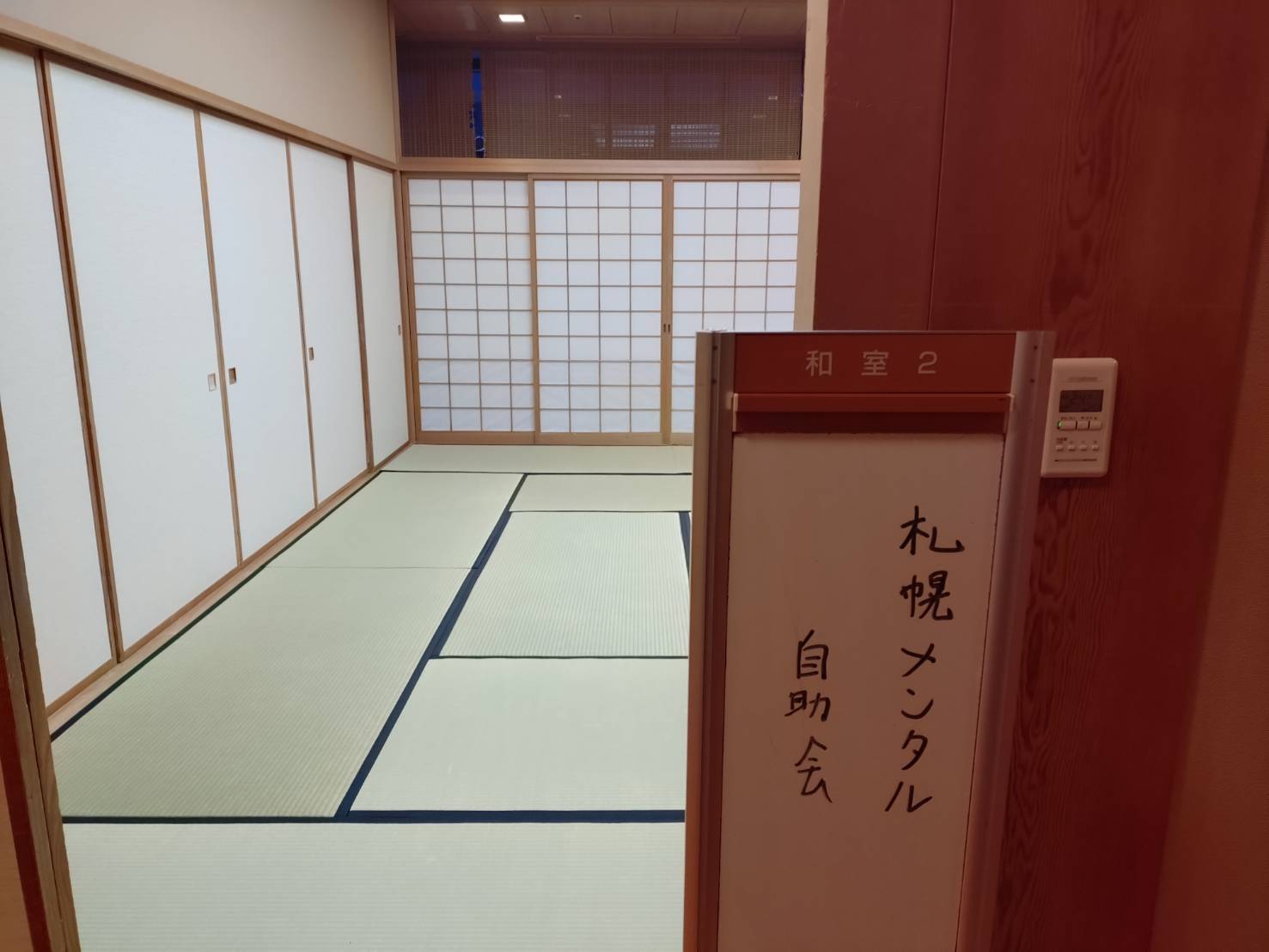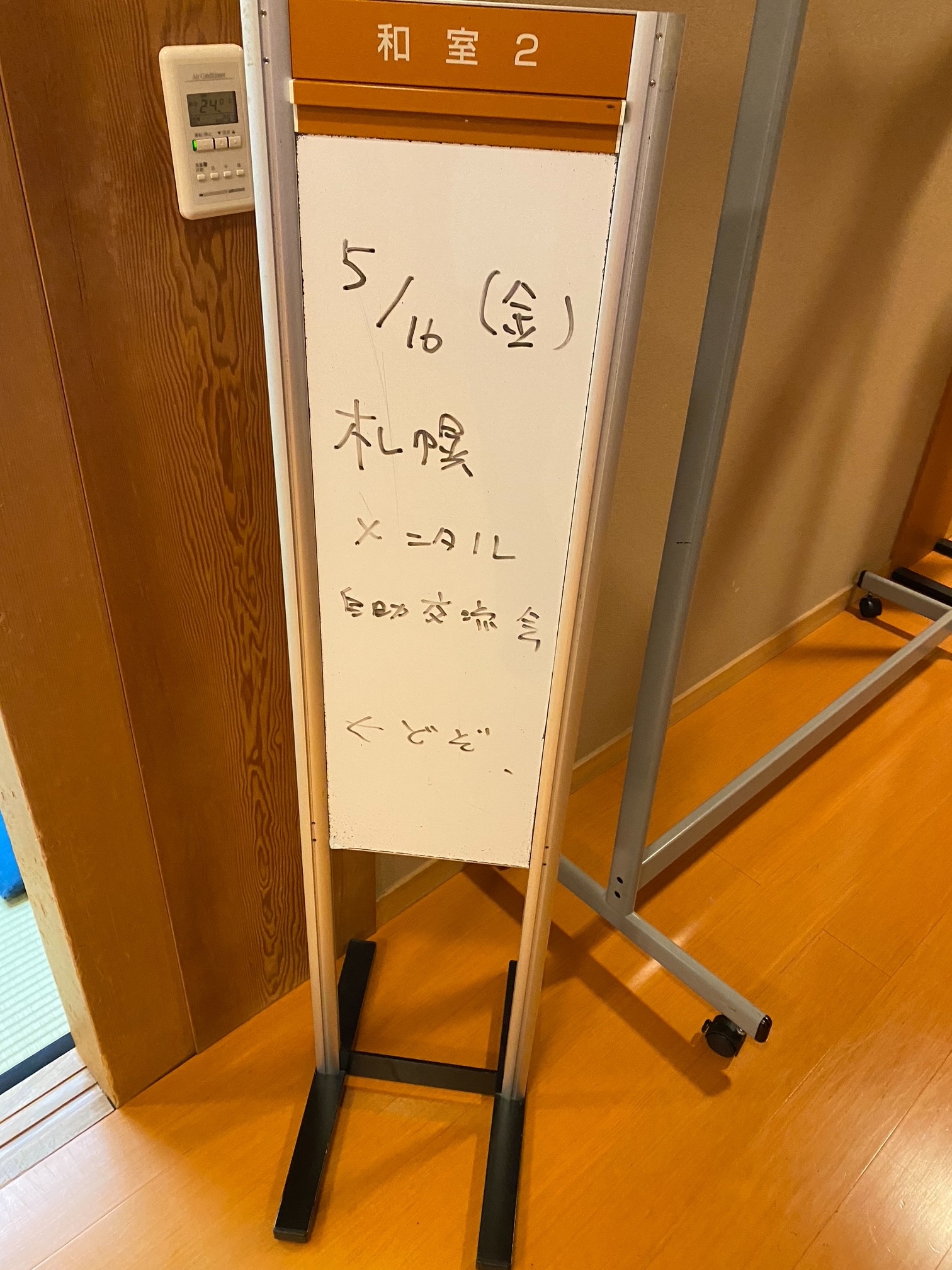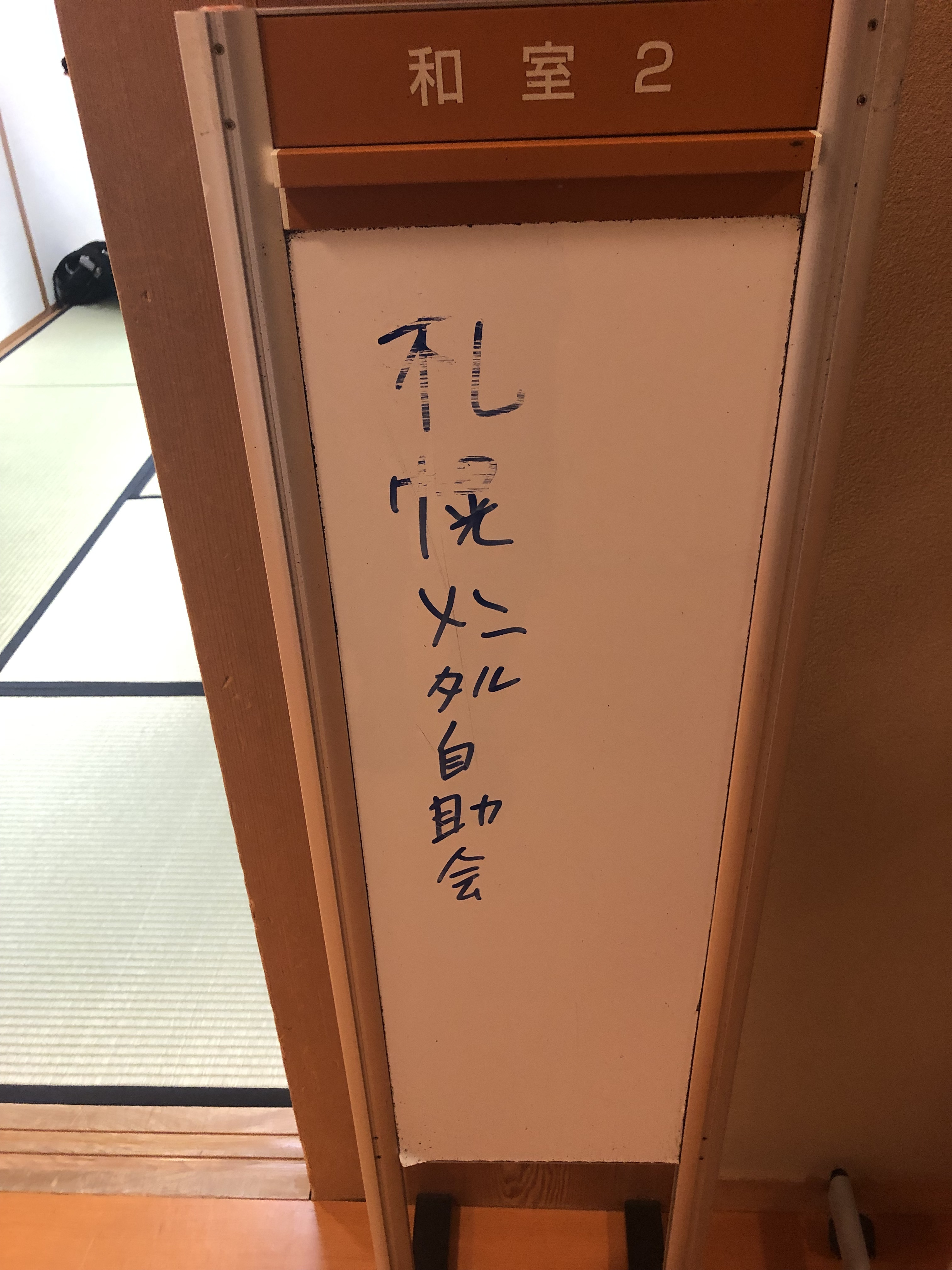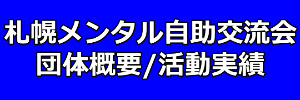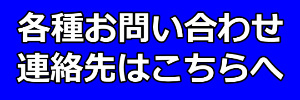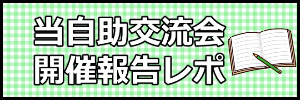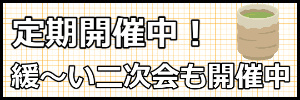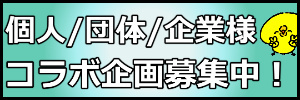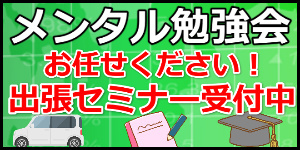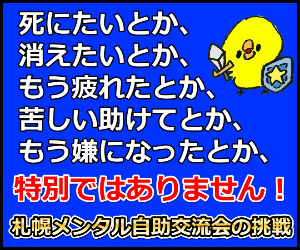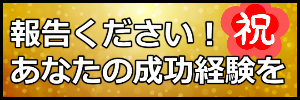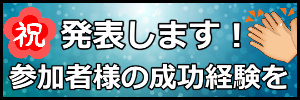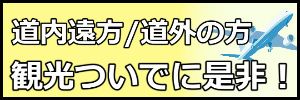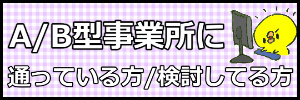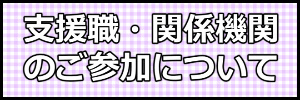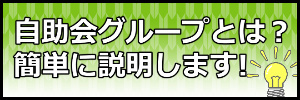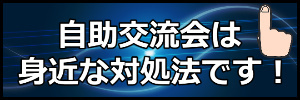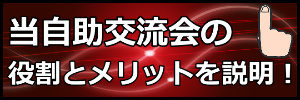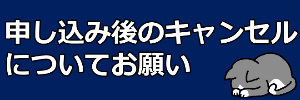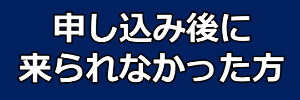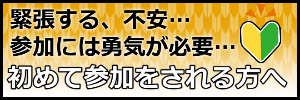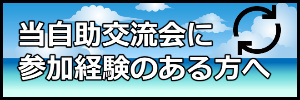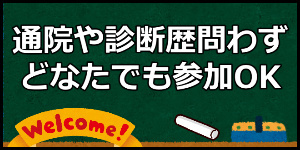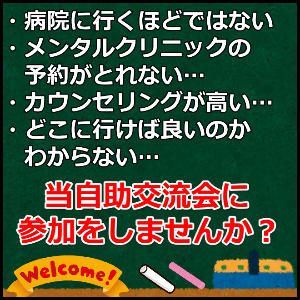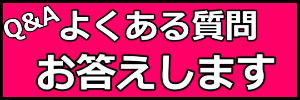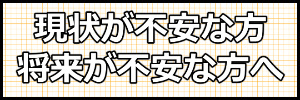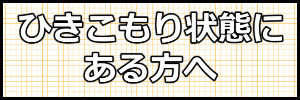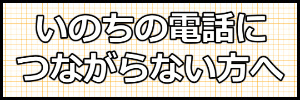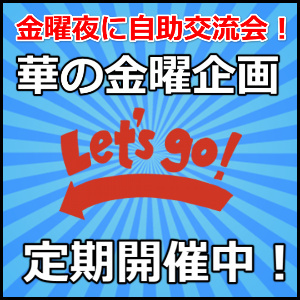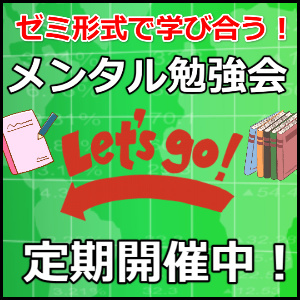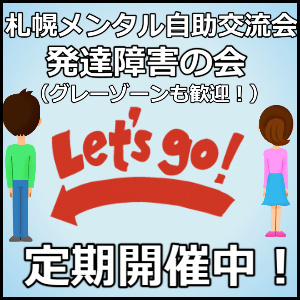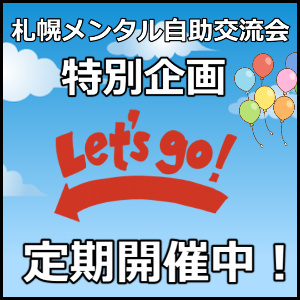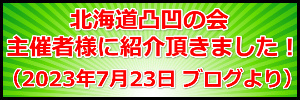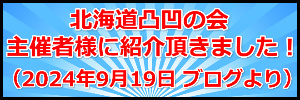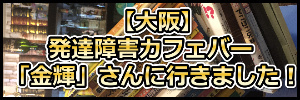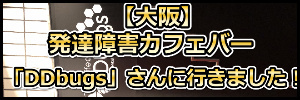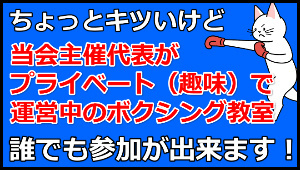札幌メンタル自助交流会vol.82を開催しました!

本日11回目のファシリテーターを務めさせていただきました。「
(1)スマホでのスケジュール管理について
【お題】私は普段、スケジュール管理のためにカレンダーアプリを
これ、めっちゃ分かります。
例えば、2025年8月1日の朝に以下の予定の通知が来たとしま
「2025年8月1日 18:00 焼き肉」
この内容でも大筋分かるとは思うのですが、よくよく考えると、2
①誰と焼肉?
友達なら多少遅れて到着してもいいのですが、職場関係なら遅れた
②どこで焼肉?
焼き肉店でしょうか。それともバーベキューでしょうか。屋内外す
≪カレンダーアプリに入力している予定の区分が一見して分かるよ
・複数のカレンダーアプリを使い分ける
・タグやグループの機能を使う
・予定の区分ごとに文字の色を変える
・予定の区分ごとに関連した絵文字を使う
・カレンダーとメモを併用する
・予定を職場のグループウェアに同期する
なお、iPhoneの場合だと「リマインダー」というアプリがあ
(2)職場環境と休職について
職場環境には大きく分けて人間関係、待遇および物理的環境の3つ
ここで分かるのは、「人間関係、待遇および物理的環境を判定する
【箇条書き】職場環境を左右する要素
・人間関係:依怙贔屓、無視、陰口、派閥
・待遇:評価や報酬の不公平、長時間労働
・物理的環境:空調や安全の不備、騒音等
何らかの理由で休職しているという方は、決して少なくはないです
(3)外出の機会について
休日などで外出をしてみると、思ったよりも色々なことに出くわす
例えば、日本語またはそれ以外の言語で道を聞かれたり。
私は、ある日、大通公園の4丁目付近で海外の人とみられる方に、
それから、道端で貴重品など、ヤバい落とし物を見つけたり。
このことをお話ししてくれた参加者さんは、きちんと、そのヤバい
(4)パソコンスキルについて
最近の就活で求められるスキルの筆頭となっているのが、パソコン
なので、その証明になるものの一つが資格です。例えば、MOS(
そのほか、1分あたりだいたい何文字を打つことができるかという
これらの情報を履歴書の資格欄、或いは職務経歴書に記載すると、
(5)処方薬とその副作用について
診療科によるかもしれませんが、ある症状に対してどのような処方
しかし処方薬の場合、その副作用も決して無視できるものではなく
≪医師により副作用のキツい処方薬の処方が続く場合≫
・セカンドオピニオンを受ける
・いっそのこと、先生を変える
(6)色々な働き方について
【箇条書き】色々な働き方
・正規社員:無期で働けるが、社畜の側面あり
・派遣社員:柔軟に働けるが、決断を迫られる
・フリーランス:自分でキャリア設定ができる
正規社員で働く場合は、職場の理念や雰囲気が自分に合っていた方
派遣社員の中でも、一般派遣の場合と、紹介予定派遣の場合で考え
フリーランスの場合は、参加者さんより「仮にその月の収入が途絶
いずれにしましても、メリットに比べて、デメリットの方が目立っ
(7)働くモチベーションについて
私が部署Aに入ったときに、上司が言っていた言葉が、印象的でし
上司「仕事って、なんでこんなにつまらないんだろうね」
これを踏まえて、私のことについて考えてみました。
私の場合、バスの運転だとか、福祉系事業所の利用者の方々との関
なので、長続きという意味においては、仕事はつまらない方がいい
また、仕事以外のことでモチベーションを発見すると、結果的に、
「仕事はダルいが、明日の仕事が終われば連休で、青ヶ島に旅に行
このようなことは、心理学であったような気がします。直接関係は
(8)頑張ろうという気持ちになれないことについて
これは多分、めちゃくちゃ頑張っている方が悩むことだと思います
例えば、Bさんが、フルマラソンに出場したとします。42.19
「いいタイムが出なかったから、今から、もう一度42.195k
読者の方々は、これに対し、Bさんに何とお声掛けをしますか?
多分、これ以上走るのは無茶だとした上で、頑張りをねぎらったり
なので、頑張ろうという気持ちになれないときは、休んでみるとい
(9)職場などでの雑談の難しさについて
ここでは、会話を円滑に進めるための話題作りのキーワードとして
「木戸に立てかけし衣食住(きどにたてかけしいしょくじゅう)」
これは、天気や趣味、ニュース、旅、知人、家庭、健康、仕事、衣
【箇条書き】木戸に立てかけし衣食住
・木:気象→天気
・戸:道楽→趣味
・に:ニュース
・立:旅
・て:て→ち→知人
・か:家庭
・け:健康
・し:仕事
・衣
・食
・住
(10)ダイエットについて
ダイエットがしたいというお話は、最近、よく聞くようになりまし
ダイエットは、単に、食事量を減らしつつ、運動量を増やすことを
例えば、食事量を減らそうと意識すると、夜中に空腹となり、その
また、ジャンクフード(カロリーや脂質、糖分を多く含むが、栄養
(11)おわりに
この日もマジメに始まり笑いで終われて、私自身、すっごく楽しか
場を盛り上げてくれているのは、やはり参加してくれている方々だ
次回は令和7年8月24日(日)、自身3度目となる気象予報士試
是非ご参加ください!では